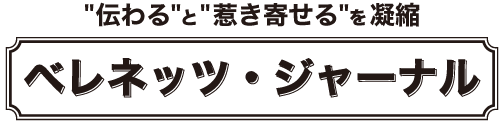「ブランディングに取り組みたいんですが...」 そう切り出すと、経営層からこんな質問が返ってきませんか? 「それで具体的にいくら売上が上がるの?」 「投資対効果はどうなの?」
マーケティング担当者なら、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
実はこれ、経営者の立場からすると当然の質問なのです。限られた予算をどこに使うべきか、常に考えなければならない立場ですから。
でも、だからといってブランディングを諦める必要はありません。今日は、経営層を説得するための実践的な方法をご紹介します。
「売上か、ブランディングか」という二項対立をやめる
まず大切なのは、「短期的な売上アップ」と「ブランディング」を対立するものと考えないこと。実は、この二つは補い合う関係なのです。
例えば、こんな風に説明してみてはどうでしょう。
「このブランディング施策には、短期的な効果と長期的な効果の両方があります。短期的には営業トークの統一により成約率が上がり、長期的には企業価値の向上で価格競争から脱却できます」
ポイントは、両方の視点を持つこと。どちらか一方ではなく、双方を実現する提案が効果的です。
「見えない価値」を「見える数字」に変換する
ブランディングは効果が見えにくいと言われますが、工夫次第で「見える化」できます。
例えば、ある製造業では次のような指標を設定しました:
・問い合わせ数の変化
・値引き要求率の変化
・採用応募者の質と量
実際、ブランディング活動を行った結果、「値引き要求が平均8%減少し、受注単価が12%向上した」という数字が出て、経営層を納得させることに成功しています。
小さく始めて、成功事例を作る
いきなり大規模なブランディング投資は難しくても、小さな実験なら承認されやすいもの。
特定の商品や地域に限定して試してみて、「このエリアでは認知度が30%向上し、新規問い合わせが15%増加しました」といった具体的な成果を示せれば、次のステップへの理解も得やすくなります。
最後に:共通言語を見つけること
経営者は「投資対効果」「リスク管理」の言語で、マーケティング担当者は「ブランド価値」「顧客体験」の言語で考えがち。
この両者をつなぐ「共通言語」を見つけることが大切です。それは「顧客生涯価値」かもしれないし、「採用コスト削減」かもしれません。
あなたの会社では、どんな「共通言語」が効果的でしょうか?ぜひ、経営者の関心事に思いを巡らせながら、最適なアプローチを見つけてみてください。
こちらには「経営陣に「ブランディングでどれだけ売上が上がるの?」と問われたときの対処法」のフルバージョンがあります。