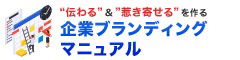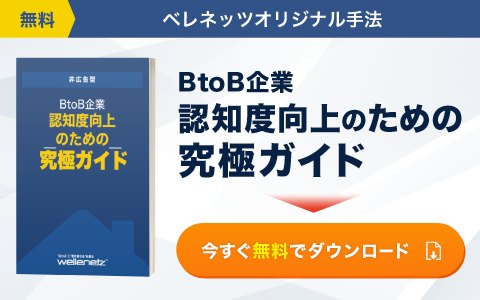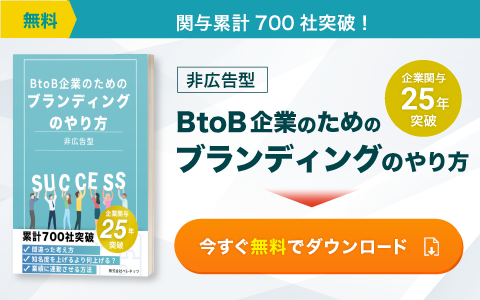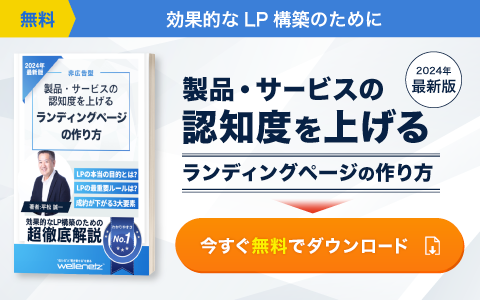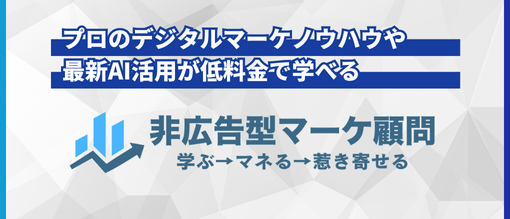「ブランディング施策をしたいのですが…」
社内で提案すると、経営層からよく返ってくるのが、「それで具体的にいくら売上が上がるの?」「投資対効果はどうなの?」という質問。ブランディングに取り組みたい担当者の多くが、この壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。
実はこれ、とても理解できる質問なのです。経営者は常に限られたリソースの最適配分を考えなければならない立場。数字で示せる施策と、ブランディングのような長期的で数値化しにくい施策のどちらに投資すべきか、悩むのは当然です。
ベレネッツでもこのような悩みが多くあります。比較的に数百億、数千億の売り上げの企業よりは、10億〜50億くらいの売り上げの会社に多く見られる現象です。そのくらいの売上高の経営者としては、次の投資の一手はROIを高めたい、一方で担当者は、「中長期的に伸びるための礎を築きたい」と考えるからです。
でも、だからといってブランディングを諦める必要はありません。今回は、経営層を説得するための実践的なアプローチをご紹介します。
1. 「売上か、ブランディングか」という二項対立から脱却する
よくある誤解は、「すぐに売上を上げる施策」と「ブランディング」を対立するものとして捉えてしまうこと。実際には、この二つは補完関係にあります。
たぶん、経営陣の中には「すぐ何かが動く」という感覚がないのでしょう。
ベレネッツには「時短ブランディング」があります。例えば、短期的と中長期でブランディングの威力を見ていきましょう。
短期的ROI
- 顧客の認識変化: 時短ブランディングによる顧客の認識変更で購買障壁を取り除き、短期間で成約率向上
- 営業プロセスの効率化: ブランドメッセージ強化による営業活動の効率向上
- リード獲得コスト削減: 惹き寄せ型アプローチによる自然な顧客獲得
中長期的ROI
- 価格競争からの脱却: 価値訴求による価格感度の低減
- 顧客生涯価値の向上: ブランドロイヤルティによるリピート率向上
- 採用力の強化: 企業価値明確化による優秀な人材の獲得
どうですか?これでもまだまだ尻込みをしますか?少なくとも、ロゴを変えたり、WEBサイトのリニューアルをするような「ブランディングっぽい」行為ではまず効果は出てきませんが、ポイントは、「短期的な売上」と「長期的なブランド構築」の両方に寄与する施策を設計し、その二面性をしっかりと伝えること。これにより、「どちらか一方」ではなく「両方を実現する」という前向きな議論ができるようになります。
2. 「見えない価値」を「見える形」に変換する
ブランディングの効果が見えにくいのは事実です。だからこそ、可能な限り「見える化」する工夫が必要になります。
ベレネッツの『時短ブランディング』と『禁断のブランディング』を導入した製造業のA社では、効果測定のために次のような指標を設定しました:
- ベレネッツのオリジナルの考え方であるT.R.U.S.T.理論による「隠れた価値」発見後の問い合わせ数の変化
- 営業活動せずに自然に集まる見込み客数(惹き寄せ効果)
- 顧客単価と値引き要求率の変化
- 採用応募者の質と量の向上
- 従業員のブランド理解度と誇り
特に経営層を納得させたのは、『禁断のブランディング』で発見した隠れた価値を訴求した結果、短期間で数値化できる成果が生まれたことでした。「従来はこちらから営業活動しないと動かなかった見込み客が、自ら問い合わせてくるようになり、営業コストが30%削減。さらに値引き要求が平均8%減少し、受注単価が12%向上しました」という報告は、ROIを重視する経営層に大きな影響を与えました。
3. 「将来のコスト削減」という視点を提示する
ブランディングを「投資」として語るだけでなく、「将来のコスト削減」という側面から説明することも効果的です。
例えば、ベレネッツの「禁断のブランディング」を導入したIT企業では、企業の隠れた価値を明確に打ち出したことで「採用広告費を前年比20%削減したにもかかわらず、応募者数が10%増加し、かつ面接通過率が向上しました」という成果につながっています。
また、「時短ブランディング」によって顧客の認識を変えることで営業プロセスも効率化されます。製造業のクライアントでは「初回商談から成約までの期間が平均20%短縮され、営業担当者一人あたりの年間成約件数が15%向上しました」という事例もあります。T.R.U.S.T.理論に基づく顧客認識の変化がもたらす「将来かかるはずだったコストの削減」は、ROIを重視する経営者にとって非常に説得力のある論点です。
4. 小さく始めて、成功事例を作る
ブランディング投資の効果を確実に把握するためには、段階的なアプローチが効果的です。まずは小規模な実証実験から始めてみてはいかがでしょうか。
例えば、特定の地域や特定の顧客セグメント向けに限定したブランディング活動を行い、その効果を測定します。「この地域では認知度が30%向上し、新規問い合わせが15%増加しました」といった具体的な成果が得られれば、次のステップへの展開がスムーズになります。
このような小さな成功体験を積み重ね、データに基づいて徐々に規模を拡大していくことで、より効果的で社内の理解も得られやすい全社的ブランディング戦略を構築することができます。
5. 競合事例と市場動向を示す
多くの経営判断と同様に、ブランディング投資においても市場全体の動向や競合他社の戦略は重要な判断材料となります。
「業界内の主要競合は近年ブランディング投資を強化しており、それが市場シェアの変動にも影響を与え始めています」「調査によれば、明確なブランド戦略を持つ企業は、顧客ロイヤルティが高く、価格競争の影響を受けにくい傾向があります」
このように、市場環境の変化と競合他社の動向を客観的に示すことで、ブランディング投資の戦略的重要性を共有することができます。
最後に:共通言語を見つける
経営者とマーケティング担当者の間にある認識のギャップを埋めるには、お互いの「言語」を理解することが大切です。
経営者は「投資対効果」「リスク管理」「リソース配分」の言語で考え、マーケティング担当者は「ブランド価値」「顧客体験」「市場での位置づけ」の言語で考えがち。
この両者をつなぐ「共通言語」を見つけることが、ブランディングへの理解を得る近道かもしれません。それは時に「顧客生涯価値」であったり、「リピート率」であったり、「採用コスト削減」であったりします。
あなたの会社では、どんな「共通言語」が効果的でしょうか? ぜひ、経営者の関心事に思いを巡らせながら、最適なアプローチを見つけてみてください。また困ったときにはベレネッツにお声がけください。経営陣も納得される効果を生み出すブランディングを進めることができます。