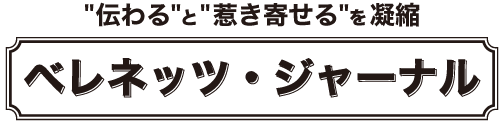from ベレネッツ代表 平松誠一
iPhone X早速契約しました。
持っている人なら分かると思いますが、
前モデルと全く違うのです。
使い方、操作方法が。
iPhoneXは、そもそも電源すらOFFにする
方法すら分からなかったり、
画面のキャプチャー方法も全然分かりませんでした。
普段は携帯ショップのスタッフに説明を聞いた
ことがない私ですら、説明を受けたくらいです。
iPhoneと言えばホームボタン。
(ちなみに、ホームボタンとは、
ディスプレイ面にボタンが1個だけ付いている
機能の中心的なボタンです。
3個ボタンのあるAndroidとは異なりますね。)
こんなメイン機能を今回ばっさりAppleは削りました。
つまり、ボタンがディスプレイ表面から消えたのです。
以前にも、Appleはこれだけ削っています。
・デスクトップPCからDVD/CDプレーヤー
・インターネット接続のためのLAN端子
・USB端子
・初代iPhoneから続いてきたケーブル
これ全部、他のパソコンではこの機能が
全盛期に削っているのです。
あなたなら、一番使われている機能を
全盛期に廃止するようなことをしますか?
これには重要な、しかしながら日本企業には
なかなか取り組めない理由があるのです。
「こうした古い技術はわれわれを引き戻そうとする。われわれの歩みに抵抗する錨なのだ。こうしたものはすでに役目を終えていると思う。競争相手は古い技術を手放すことを恐れているが、われわれはより優れた解決策を見つけ出そうとしている。顧客はわれわれに大きな信頼を寄せてくれている」
これはAppleの上級副社長フィル・シラーの言葉です。
Appleはすでに全盛期を迎え、どこでも使われるように
なった技術を「役目を終えている」と断言。
しかも顧客は「より優れた解決策を探している」
と言っているのです。
こんな決断できますか?
日本企業の場合、多い形が「最大に顧客にリーチできる
ように努力する」。
つまり、マジョリティに好かれるように努力するのです。
逆に欧米の企業は、全部とは言いませんが、
「うちはこれ!」というところが際立つまで
余分なものを排除していくのです。
マジョリティに好かれることよりは、分かってくれる人
を重要視します。
これは少し「全盛期のものを廃止する」とは
違うようなイメージがしますが、根は同じだと
思います。
分かりやすい例がIT企業です。
Twitter・・・140文字伝えるだけ。
Google・・・あのスカスカなTOPページ!
Uber・・・車の行き先指定するだけ!
これらのサービスを日本の大手企業が作れば
どうなっていたでしょうか?
たぶんこてこてにフル機能を入れてきたでしょう。
結果的にiPhone Xはホームボタンを廃止することで
FaceIDという顔認証の利便性が堪能できましたし、
クリックすることなく、ノータッチで次の機能に
進むことができるという生産性を手に入れることが
できました。
だからこそAppleは熱狂的とも言われるファンが
付くのですね。
最近は日本のベンチャー企業も「そぎ落として
めちゃくちゃシンプル」というものが多くなってきました。
名刺サービスのサンサンのeightもそうですし、
帳簿作成が簡単にできるフリーもそうですね。
あなたの会社も今一度見直して見ましょう。
削っていくことで、いままで隠れていた魅力が
浮上してきますよ。
ちなみに、弊社の顧客でも、アパレルでいらない特色を
削りまくり、ある分野で圧倒的にトップになっている
メーカーや、小売業で不必要な要素を後ろに持っていき、
力を抜いたことで、結果的にある分野で日本一位になりました。
さぁ、削りましょうよ。