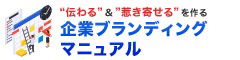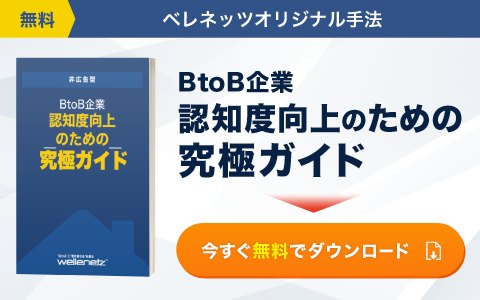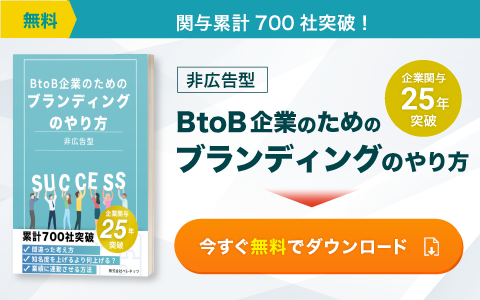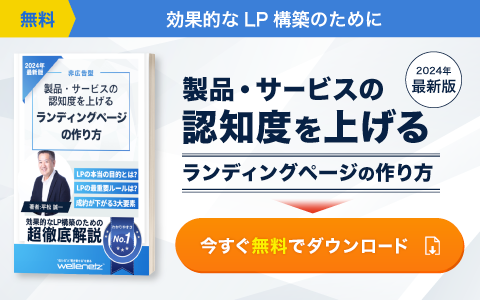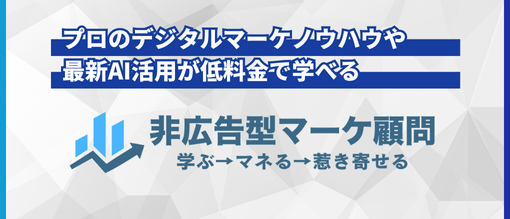なぜ今、ブランディングが重要なのか
情報があふれる現代において、消費者は日々大量の選択肢にさらされています。スマートフォンを開けば無数の広告が流れ、SNSでは競合他社の投稿が次々と目に飛び込んできます。
このような状況で選ばれる企業になるには、価格やスペックだけの競争から抜け出す必要があります。「この会社だから選びたい」と思わせる存在感——これがブランド価値です。
実は、人間の脳は意思決定の95%を無意識のうちに行っています。顧客があなたの企業を選ぶかどうかは、論理的な判断よりも、感情や直感が大きく影響しているのです。
なぜ多くの企業がブランディングに注目しているのか
近年、次のような課題を抱える企業がブランディングに取り組み始めています。
- ライバル企業と比較して認知度が圧倒的に低い
- 商品やサービスの魅力が顧客にうまく伝わらない
- 価格競争に巻き込まれ、利益率が圧迫されている
- 採用活動がうまくいかず、若手人材が集まらない
- 自社の強みが言語化されておらず、差別化できていない
これらは「ブランド」が確立されていないことで起きている問題です。広告やPRといった表面的な施策では解決できません。根本的な価値伝達の設計が必要なのです。
ブランディングは「イメージ戦略」ではない
「ブランディング」と聞くと、ロゴデザインの変更やWebサイトの刷新を思い浮かべる方が多いかもしれません。確かにそれらも手段の一つですが、本質はもっと深いところにあります。
根本にあるべきなのは「何を、誰に、どう伝えるのか」というコミュニケーション戦略であり、企業の存在価値そのものを見つめ直すプロセスです。
外注によるブランディングを検討する際、多くの企業がこの本質的な視点を欠いたまま依頼してしまいます。その結果、見た目だけは整った「なんとなくかっこいい」成果物が生まれるものの、期待した効果は得られません。
このコラムでは、企業がブランディングを外注する際に陥りがちな落とし穴や、依頼時に押さえておくべきポイントを体系的に解説します。
こんな悩みがあるならブランディングを検討すべき
企業がブランディングを検討するきっかけはさまざまですが、共通しているのは「現状、何かがうまくいっていない」という感覚です。ブランディングによって改善が期待できる代表的な悩みを見ていきましょう。
1. ライバルに認知度で負けている
「うちの製品の方が性能も価格も優れているのに、なぜ競合の方が選ばれているのか?」
これは、製品比較の問題ではなく、ブランドとしての存在感が市場で認識されていないことが原因です。企業名やサービス名を見ただけで「信頼できそう」「プロっぽい」「あそこなら安良いモノを作っているのに売れない。その背景には、情報伝達の欠如があります。
広報活動や広告だけでなく、「なぜこの商品が存在しているのか」「どのような価値を提供するのか」を一貫したストーリーとして伝える設計が必要です。これを整理・体系化するのがブランディングの役割です。心」と感じてもらえる状態——これがブランディングの成果です。
2. 商品・サービスの魅力が知られていない
良いモノを作っているのに売れない——その背景には、情報伝達の欠如があります。単なる広報活動や広告ではなく、「なぜこの商品が存在しているのか」「どのような価値を提供するのか」を一貫したストーリーとして伝える設計が必要です。
これを整理・体系化するのがブランディングの役割です。
3. 価格競争に巻き込まれている
価格でしか勝負できない状態は、ブランドが機能していないサインです。
確立されたブランドは、多少価格が高くても選ばれる理由を持っています。AppleやStarbucksはその典型例ですが、中小企業でも「価値で選ばれる企業」になることは十分可能です。
4. 採用活動がうまくいかない
採用におけるブランディングは「採用ブランディング」として独立した重要分野です。
応募者は企業のWebサイト、SNS、口コミなどから企業の雰囲気や価値観を無意識に読み取っています。魅力的なブランドは、人材確保の競争でも大きな武器になります。
5. 自社の強みが伝わっていない
「社内では強みとされていることが、なぜか顧客に伝わらない」
これは主に言語化・表現の不一致によるものです。自社が本当に届けたい価値を、顧客視点に変換して伝える設計力が求められます。内製だけで行うのは難しく、外部のブランディングパートナーが役立つ場面です。
よくある失敗例:手段が目的化したブランディングの落とし穴
ブランディングを外部に依頼する際、最も多い失敗パターンの一つが「手段と目的の混同」です。
見た目の刷新や流行のデザインを優先するあまり、本来のブランド価値の再定義や、顧客との関係性の構築といった本質的な目的が置き去りにされてしまうケースは少なくありません。
1. 「ロゴを新しくすれば変わる」という誤解
外注先の提案でありがちなのが、「まずはロゴを刷新しましょう」というアプローチです。
確かに、ロゴはブランドイメージを象徴する重要な要素ではあります。しかし、それ単体でブランディングが完結するわけではありません。むしろ、ロゴ変更が逆効果になることもあります。
企業文化や商品価値が定まっていない状態で見た目だけを刷新すると、既存顧客にとっては「なんとなく変わってしまった」という違和感しか残らず、信頼感が損なわれるリスクもあるのです。
2. Webリニューアルにすべてを賭ける
Webサイトを一新すればブランドが強化される——そう考えて全面リニューアルを進めたものの、アクセス数やコンバージョン率がむしろ下がってしまった例は少なくありません。
問題は、リニューアルにあたって「何を伝えたいのか」「誰にとってどういう価値があるのか」といったブランドのコアメッセージが定義されていなかったことにあります。
結果として、表面的には美しくなったものの、「伝えるべき中身がない」状態になり、ユーザーにとっては魅力を感じないサイトになってしまうのです。
3. 社名変更やスローガン刷新の落とし穴
大胆なリブランディングとして、社名の変更やスローガンの刷新を行う企業もあります。しかし、これも慎重に行うべき施策です。
表層的に「新しさ」や「勢い」を打ち出したつもりでも、それが社員や顧客にとって意味のある変化でなければ、単なる自己満足に終わってしまいます。
特に、社名やスローガンの変更は、社内外のステークホルダーに混乱を招く可能性があるため、それを上回るだけの説得力と一貫したブランドストーリーが求められます。
成功のカギは「本質的な目的」を問い続けること
いずれの例にも共通しているのは、「なぜこれをやるのか?」という問いに対する明確な答えが欠けていたことです。
見た目や流行、外注先の提案に流されるのではなく、常に「自社が誰に、どんな価値を届けたいのか?」という目的ドリブンの視点を持ち続けることが、成功するブランディングの前提条件です。
ブランディングを依頼する前に整理すべき自社の情報
ブランディングを外部に依頼する際、最初の打ち合わせで「何をどう伝えるべきか分からない」という状態では、的確なアウトプットは望めません。
よいブランディングパートナーを見つけても、自社の提供価値や現状の課題が曖昧なままでは、ブレのある成果物になってしまいます。依頼前に企業側が準備・整理しておくべき重要情報について解説します。
1. 現在抱えている課題の明確化
ブランディングを依頼する背景には、必ず「解決したい悩み」があるはずです。
それが漠然と「売上が伸びない」「採用に困っている」といった表現では、ブランディング会社は対応のしようがありません。
以下のように、できるだけ具体的に課題を言語化することが必要です。
- 社員が自社の強みをうまく説明できていない
- 顧客から「〇〇な印象」を持たれているが、本当は△△を伝えたい
- 顧客層が価格重視層に偏っており、ブランド価値が浸透していない
- 採用応募者が業界認知度の低さで集まらない
2. 自社の「強み」や「独自性」の棚卸し
ブランディングの基本は、「自社が選ばれる理由を明確にすること」です。外部の力を借りるにしても、企業内部で「何が強みなのか」「他社とどう違うのか」という棚卸しは避けて通れません。
強みとは、商品スペックだけではなく、次のようなものも含まれます。
- 創業の背景や理念
- 社員の姿勢や文化
- 顧客から寄せられる具体的な評価
- サービス提供の流れや独自の体験価値
こうした情報は、外部からは見えにくいため、企業自身が語れる状態にしておくことが必須です。
3. 現在のブランド資産・認知状況
今あるロゴ、キャッチコピー、Webサイト、SNS、会社案内、採用パンフレットなど、ブランドとしての接点(タッチポイント)がどうなっているかを整理しておきましょう。
また、既存顧客がどのように自社を認識しているか、アンケートや営業現場の声なども貴重なデータになります。
これらは、リブランディングの出発点として非常に有効です。
4. ブランドのゴールイメージを言語化する
理想的には、「〇年後にこういうブランドとして認知されていたい」「このような顧客層に支持されたい」というブランドのビジョンがあると、外部パートナーとの認識ズレを防ぐことができます。
完璧な戦略である必要はありません。むしろ、理想の状態を素直に共有することで、パートナーは適切な方法でそれを形にしてくれます。
依頼前にこれらを整理することで、ブランディング施策の精度とスピードが大きく向上します。また、プロジェクトの進行中に軸がブレにくくなり、社内の合意形成も取りやすくなるのです。
信頼できるブランディング会社の選び方
ブランディングの成否は、誰に依頼するかで大きく左右されます。見た目が美しいだけの提案に惑わされず、課題解決型の視点を持つパートナーを選ぶことが重要です。
この章では、信頼できるブランディング会社を見極めるためのチェックポイントを解説します。
1. 表層的な提案に終始していないか
ブランディング会社の提案が「ロゴを新しくしましょう」「Webサイトをおしゃれにしましょう」といったビジュアル面の刷新に偏っている場合、注意が必要です。課題の本質に踏み込まず、見た目だけを変えるアプローチは、長期的な効果が期待できません。
本当に信頼できる会社は、まずヒアリングで「なぜそれが必要なのか」「何を解決したいのか」という課題設定から始めます。ロゴやWebの話が初期段階で出てくる場合、その会社は“手段主導”の可能性があります。
2. 戦略設計力があるか
ブランディングは、デザインやコピーの前に「戦略」が必要です。ターゲット顧客、競合との差別化、提供価値の明確化、伝えるメッセージ設計など、ロジカルな思考力と分析力を持ったチームがいるかを確認しましょう。
具体的には、以下のようなフローを提案してくれる会社は信頼できます:
- 現状分析(ブランド監査)
- インタビュー・市場調査
- ポジショニング設計
- ブランド・ステートメントの定義
- クリエイティブ設計
3. 実績とその「プロセス」を確認する
過去の実績は重要ですが、それ以上に「どのようなプロセスで成果に至ったのか」を確認することが大切です。
単なるビフォーアフターのデザイン事例だけでなく、課題→提案→成果のプロセスを提示できる会社は、信頼性が高いです。
また、同業界・同規模の企業を手掛けた経験があるかどうかも、判断材料になります。
4. コミュニケーションスタイルの確認
プロジェクトは数ヶ月にわたることが多く、パートナーとの相性も成功に大きく関わります。初回の打ち合わせやメールのやりとりで、次のような点をチェックしておきましょう:
- ヒアリングが的確か
- 説明が論理的でわかりやすいか
- 課題に対して深く掘り下げてくれるか
- 一方的に提案を押し付けてこないか
良いパートナーは、「共に考える姿勢」を持っているものです。
5. 見積もりが透明かつ根拠があるか
ブランディングは価格の相場感がつかみにくいため、金額の内訳が明確で説明責任を果たせるかは非常に重要です。「なぜこの価格なのか」がきちんと説明されない場合、その後のトラブルにもつながりかねません。
信頼できるブランディング会社は、単に“制作”を請け負うのではなく、企業と伴走しながら価値を言語化し、戦略として落とし込んでいく存在です。その見極めには、提案書の表面だけでなく、ヒアリングや会話の質に注目することが成功への第一歩です。
打ち合わせ・要件定義で伝えるべき「課題」と「期待」
ブランディングの依頼は、単なる制作発注とは異なります。ブランディング会社は「自社の価値を再定義するパートナー」であるため、最初の打ち合わせでどれだけ自社の課題や期待を正しく伝えられるかが、その後のプロジェクトの方向性と成果を大きく左右します。
この章では、初回ヒアリングや要件定義の場面で企業側が意識すべき重要な伝達ポイントを整理します。
1. 抱えている課題を具体的に共有する
「売上が伸びない」「イメージを変えたい」といった抽象的な要望だけでは、適切な施策は設計できません。以下のように、課題の背景や影響を具体的に伝えることが重要です。
- 「競合A社と比較して指名買いされる率が明らかに低い」
- 「リブランディング後も、ターゲットユーザーから反応がない」
- 「自社の強みが営業資料にもWebにも表現されていない」
こうした具体例があれば、ブランディング会社は原因を特定しやすくなり、的確なアプローチを提案できます。
2. 期待している成果やゴールを共有する
ゴールが曖昧なままでは、方向性のズレが生まれやすくなります。たとえざっくりとした内容でも、「どんな状態になれば成功といえるのか」を共有しましょう。
- 「指名検索される企業になりたい」
- 「価格競争から脱却し、“価値で選ばれる”ブランドにしたい」
- 「若手人材にとって魅力的な企業イメージを構築したい」
このように、期待のベクトルを示すことが、外部パートナーとの共通認識づくりに不可欠です。
3. 手段へのこだわりより、目的を共有する
ありがちな失敗は、「ロゴを変えたい」「Webをリニューアルしたい」という手段ありきの要望になってしまうことです。
ブランディングのプロセスでは、「なぜそうしたいのか」「何を実現したいのか」という目的をベースに議論を進める必要があります。
ブランディング会社にとっては、ロゴ変更やWeb制作は“結果として最適なら行う手段”にすぎません。
目的を伝えずに手段を指定すると、効果の薄い施策に終わるリスクが高まります。
4. 社内の合意形成状況も伝える
プロジェクト推進には社内体制の影響も大きいため、以下の点も初期段階で共有しておくとスムーズです。
- 意思決定者は誰か
- 担当部署の温度感
- 社内でどのような議論があったか
- 抵抗感のある層が存在するかどうか
このような情報を事前に共有しておくことで、ブランディング会社も**“通りやすい提案の仕方”**を設計することができます。
良いブランディングは、企業と外部パートナーの双方向の対話と共創から生まれます。そのためには、初期段階で企業側が「何を解決したいのか」「どこを目指したいのか」を率直に伝えることが最も重要なのです。
成果を最大化するための社内体制と継続的な関わり方
ブランディングのプロジェクトは、ブランディング会社に依頼すれば完了するものではありません。
むしろ、依頼後の企業側の関わり方や社内体制のあり方が、成果に大きな影響を及ぼします。
ここでは、ブランディングを“自社の血肉”として根付かせるために必要なポイントを解説します。
1. 丸投げは禁物。「共創」のスタンスを持つ
多くの企業が犯す最大の失敗は、「外部のプロに頼んだから任せておけばいい」という姿勢です。しかし、ブランディングは企業の“内面”に深く踏み込むプロセスであり、企業自身が語れないブランドは外注先にも作れません。
外部パートナーとは、「調査・整理・表現」の過程を一緒に設計していく必要があります。企業側が積極的に参加し、判断し、フィードバックを返すことで、初めて本質的なアウトプットが可能になります。
2. 社内に“理解者”と“推進者”を配置する
ブランディングは、全社を巻き込むプロジェクトになりがちですが、実務を担う担当者が孤立してしまうケースも少なくありません。成功のためには、次のような体制が必要です。
- 経営層の理解と関与:ブランディングは経営判断であり、トップの関与が不可欠
- 現場との橋渡し役:マーケティング・営業・人事など、各部署と連携できる担当者
- 社内浸透を意識した担当者:外部アウトプットだけでなく、社内向け展開も視野に
プロジェクトリーダーは、デザインやマーケティングの知識以上に、社内調整力と理念への共感力が求められます。
3. ブランディングの成果を「運用」に落とし込む
完成したブランドガイドラインや新たなメッセージは、発表して終わりではなく、あらゆる接点で一貫して運用することが求められます。
- WebサイトやSNSのトーン&マナー
- 営業資料・提案書の表現
- 採用パンフレットや会社説明会の内容
- 社員教育や社内報
これらにブランド戦略が浸透して初めて、「企業としての一貫した印象」が形成され、対外的な信頼へとつながっていきます。
4. 継続的なレビューと改善の仕組みを持つ
ブランドの価値は時代や市場の変化とともに変化します。最初に設計したブランドが常に正しいとは限りません。定期的に効果測定や社内外のフィードバックを取り入れ、**「育てるブランディング」**として長期的に取り組むことが、ブランドの持続的成長を支えます。
ブランディングは単なるプロジェクトではなく、「企業文化と価値観の再定義」であり、「顧客との関係性の設計」です。そのためには、外部に依頼した後こそが本当の勝負です。企業自身が主体となって、ブランディングを推進する体制と姿勢を持つことが成功の鍵となります。
まとめ:成功するブランディング依頼の鉄則とは
本コラムでは、企業がブランディングを外部に依頼する際に陥りやすい失敗と、その回避策について段階的に解説してきました。最後に、成功するブランディング依頼に共通する「7つの鉄則」をまとめておきます。
1. 「見た目」ではなく「目的」からスタートせよ
ロゴやWebリニューアルは手段でしかありません。なぜブランディングをしたいのか、何を解決したいのかという目的起点でプロジェクトを始めましょう。
2. 抱えている「悩み」を具体的に言語化せよ
「競合より目立たない」「強みが伝わらない」「価格競争に苦しんでいる」など、自社が感じている課題を曖昧にせず、具体的な事実や影響とともに伝えることが成功への第一歩です。
3. 自社の「強み」や「独自性」を棚卸しせよ
ブランディングは“創る”というより“引き出す”作業です。企業の歴史や文化、商品が持つ価値など、内側にある本質を言語化できる準備を整えましょう。
4. パートナー選定では「戦略性」と「共創力」で見極めよ
実績やデザイン力だけでなく、「戦略的思考があるか」「伴走してくれる姿勢があるか」を重視しましょう。信頼できるパートナーは“共に考える存在”です。
5. 打ち合わせでは「期待する成果」を率直に伝えよ
ゴールが見えなければ、的確なアプローチは不可能です。「どんな状態になれば成功か?」という成果イメージを共有することが、ブレないプロジェクトを実現します。
6. 成功の鍵は「社内の体制と巻き込み力」にあり
担当者任せではなく、経営層と現場をつなぎながら組織全体でブランディングに向き合う意識を醸成しましょう。推進者と理解者の両輪が不可欠です。
7. ブランドは「育てるもの」であると理解せよ
ブランディングは一度完成して終わりではありません。運用・改善・定着のプロセスこそがブランド価値を高めていきます。“運用する覚悟”が成果を生み出します。
終わりに
ブランディングとは、企業の「あり方」を明確にし、顧客・社員・社会に一貫して伝えていく営みです。外部に依頼する際には、単なるデザインの発注ではなく、自社の価値と未来を共に考えるパートナー選びと、社内体制づくりが成功のカギを握ります。
この記事を通じて、読者の皆様が自信を持ってブランディングを依頼し、長期的な企業価値の向上につなげていただければ幸いです。
「禁断のブランディング」「時短ブランディング」という特別な企業ブランディング手法を持ったベレネッツでは、無料1on1オンラインセミナーを開催しております。
こちらからお申し込みください