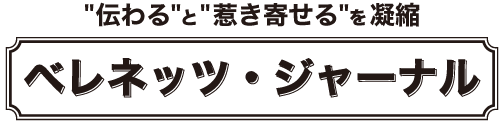From 代表・平松
ベレネッツ代表の平松です。
主に、経営者/経営陣に役立つ内容を毎週お送りします。
さて、今回よりメルマガを2種類に分けました。
理由としては、ベレネッツのメルマガを読んでいる方が全く違うタイプが存在することがずっと気になっていたからです。
大きく分けると以下の2タイプあります。
1. 経営者、もしくは経営陣で会社全体の戦略を考える/実行する立場の人
2. マーケティング、特にWEBマーケティングに関わり、集客やCVなどに責任を持つ人
さて、それぞれどんな悩みがあるのでしょう?
経営陣の悩み

1の方の経営陣からよくある悩みは
・どのように自社の認知度を上げていくか
・商品/サービスをターゲット層にどのように気づかせるか
・負けている商品/サービスをどのように挽回するのか
・良い商品/サービスなので今ひとつ売れない理由を突き止めたい
など、比較的解決に時間を要するものが多いです。
WEB関係の担当者の悩み

逆に2の方のWEB関係の担当者の方からは
・Googleでの順位を上げていきたい
・WEBの対策をしているがユーザーに読んでもらえない
・CVが悪い
・Googleアップデートで順位が下がった上での対策
・最新のWEBマーケティングのやり方
など、速攻で効く「手法」を聞かれる方が多いです。
つまり、全然求めているものが違うのです。
さて、本日は、経営に役立つブランディングのやり方は?
という経営陣むけのテーマを話します。
重要なことは5つ。
① プッシュしない。
広告に出稿し、社名をひたすら覚えさせることがブランディングと思っている人がいますが、全く違います。
プッシュではなく、プルで認知させることがブランディングです。
② デザインを変えただけで満足しない。
WEBサイトのリニューアルや、ロゴデザインの変更、社名の変更がブランディングと考えているならば、大間違いです。
デザインを変えることはブランディングではありません。
③ BtoC企業に役立つのがブランディングで、BtoBには関係ないと思わない。
この考えはだいぶ少なくなってきましたが、相変わらず「固定顧客との取引関係ばかりなのでブランディングは必要ない」という経営陣はいます。
新たに顧客を増やしたくなければブランディングは必要ないですが、新規顧客を増やしたい、価格を上げたい、違う認識をされたい、と思うのであれば、BtoB企業でもブランディングは必要です。
④ ブランディングにはあまり投資したくない、というのは誤った判断。
一部上場企業でもこのような考え方の経営陣はいます。
投資することなく、認知度が上がり、競争優位性ができるような市場はあっという間に淘汰される脆弱なところでしょう。
もしくは、投資しなければリターンはないので、ずっと認知は上がらないままでしょう。
この考え方は完全に間違っています。
⑤ 丸投げでどこかのプロにブランディングをやってもらえばOK、は誤った考え方。
皆さんの会社です。皆さんの商品/サービスです。
それらの認知度を上げたり、見込み客に真の差別化要素を理解させたりする部分を外の業者に丸投げしないでください。
そこまで命を預けて大丈夫ですか、と言いたいです。
丸投げで大丈夫、なんていう業者ではなく、一緒にやっていきましょう、という業者を選びましょう。